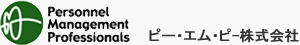働き方改革やら36協定の上限規制等々、労働法改正に関係する話題には事欠かない昨今ですが、
実はこれらを支える改正法案はいまだに作成されていません。
改正労働法についていえば、2-3年前から国会に上がっているものの審議入りすらされておら
ず、労働基準法改正法案(働き方改革や36協定の上限規制以前の法案)も、この通常国会でも
棚ざらし状態です。
後半の国会も重要法案の審議が控えており、労働法改正まで手がつけられるかは不明という心も
とない状況です。
そんな状況で、過重労働の防止を意識してか、厚労省はこの度、「労働時間の適正な把握のため
に使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発表しました。
人事労務の実務を司る皆さんには、是非、関心を払って頂きたい内容です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
当ガイドラインは、これまでの“46通達”「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関する基準(平成13年4月6日付基発339号」を廃止し、これに書き換えられたものです。
したがって、46通達内容を踏襲しつつ、一部改訂、一部補足した内容となっています。
当ガイドラインの主要変更点は以下のとおりです。
1. 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間である(三菱重工長崎造船所事件平成
12年3月9日最高裁)として、使用者から明示された就業前準備行為時間、手待ち時間、
受講が義務付けられている研修時間という事例をあげながら、労働時間に該当するか否かは
客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれているかを、労働者の行為が使用者から義務付け
られ、または余儀なくされているか等の状況の有無等から個別具体的に判断するとしている。
2. 労働時間の適正な記録手段として、従来からのタイムカード、ICカードという記載に加えて、
パソコン使用時間の記録を加えた。
3. 自己申告制で確認・記録を行う場合に講ずべき措置に、次の内容が追加された。
・実際の労働時間を管理する者に、自己申告制の適正な運用を含めて、ガイドラインに従って
講ずべき措置を十分説明すること
・自己申告時間を超えて事業場内にいる時間について、労働者にその理由等を報告させる場合
は、その報告が適正に行われているか確認すること
・36協定により延長可能な時間を実態として超えて働いているにも関わらず、記録上は協定
を守っているようにすることが慣習的に行われていないか確認すること
また、上記2のような記録と労働者からの申告された労働時間の間に著しい乖離がある場合、
実態調査を行い、労働時間の適正な補正をすることとしている。
追記として、休憩や自主的な研修・教育訓練という報告であっても、使用者の指揮命令下に置
かれていると認められる場合は労働時間とするとしている。
4. 労基法第108条、同施行規則第54条を踏まえて、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、
時間外労働時間数、深夜労働時間数を賃金台帳に正確に記載するという賃金台帳の調整義務に
ついても触れている。
振り返れば、これまでの個別の労働基準監督官の立入検査時に、各監督官から指摘されたことの
あった事項が改めて網羅的に正式文書に記載されたもののように思えます。
その点では諸氏には、別に目新しく特別な指導項目が追加されたものではないと思われるかもしれ
ません。
しかしながら、今後の立入検査では、ここに挙げられた事項については直ちに是正勧告あるいは指
導票となるリスクが高まったとして、社内の運用管理を見直される事をお勧めします。
実際の労働時間の管理に際しては、これまで以上に厳格に対応する必要があると思われます。
また、PMPコンサルタントは経験豊富な特定社会保険労務士や監督署対応で苦労を重ねた各社人事
部長のOB・OG集団ですが、彼らによる、労働時間管理の労務監査サービスを新しく開始しました。
ご関心のある方はPMPまでご照会ください。
※本件に対するご質問、お問い合わせはお気軽にPMP(info@pmp.co.jp )までお寄せください。
※今後PMPからの情報発信が不要な場合は、大変お手数ですが、その旨をこのメールへの返信で
お知らせください。